普段、多くのギタリストやベーシストが何気なく使っている「オートワウ」という言葉。
しかし、この呼び名には少なからず誤解を招きやすい要素があります。
ちょっとしたきっかけがあったので、今回はこの「オートワウ」という言葉について整理してみようと思います。
「演奏に応じてワウがかかるエフェクター」の呼び名
私自身、過去に「オートワウ」と呼ばれるエフェクターをいくつか所有してきましたが、このブログでは、「エンヴェロープフィルター」のタグをつけて分類しています。
この「オートワウ」という単語と「エンヴェロープフィルター」という単語、同じものを指すことも多いのですが、たまに違うものを指す場合もあったりしてややこしいのです。
「オートワウ」あるいは「エンヴェロープフィルター」というと、多くの場合、いずれも演奏(入力される信号)の強弱に応じて「ワウッ!ワウッ!」というワウの効果がかかってくれるエフェクターのことを指します。
「タッチワウ」という呼び方もあります。
定番人気のエレハモのMicro Q-TronとMXRのM82が登場するこちらの動画を見ると、その効果が非常に分かりやすいです。
演奏と関係なく周期的にワウがかかるエフェクター
一方、これとは違う意味での「オートワウ」もあります。
それが、コーラスやフランジャーといったモジュレーションエフェクターと同じく、LFOと呼ばれる仕組みを用いて、弦を弾かなくても一定の周期で自動的に「わうんわうんわうんわうん」とワウがかかるエフェクターです。
その機能が搭載されているエフェクターは多くありませんが、有名どころだとBOSSのAW-3 Dynamic Wahが挙げられます。
こちらの動画、冒頭からそのTEMPOモードの音です。
また、Electro HarmonixのBLURSTはその機能に特化している珍しいエフェクターですね。
ということで、「オートワウとは何か?」という質問に対しては、2種類の回答がありえるということになります。
海外でどう呼ばれているのかもちょっと調べたんですが、やはり同じエフェクターについて「Auto Wah」や「Envelope Filter」という呼び方が混在しているようです。
このブログにおいては、紛らわしくないよう、演奏の強弱に応じて作動する方のエフェクターのことは「エンヴェロープフィルター」と呼ぶように統一しています。
モジュレーションの仕組みで自動でワウが開閉するエフェクターについては、「モジュレーションワウ」とか「モジュレーションフィルター」という呼称もあるようですが、定着しているとは言えないのが現状です。
まあ製品自体が少ないので仕方ないかもしれませんね。
BOSSの新製品
で、なぜこんな記事を書こうと思ったかというと、思わぬタイミングでオートワウ(モジュレーションワウ)の機能を持つ新製品を目にしたためです。
BOSSが先日発表した新製品、200シリーズの中にモジュレーションエフェクターのMD-200という機種があるのですが、なんとコーラス等に混じって「AUTO WAH」の機能があるではないですか。
使いどころの難しいエフェクトだと思いますが、ハマれば面白いので、これでこの手のエフェクターの知名度が上がればな、と勝手に思っています。
なお、「歪みエフェクターとエンヴェロープフィルターを併用しつつ、歯切れのよいワウ効果を得るためには」という点について過去記事で書いていますので、この手のエフェクターが好きな方はご一読いただければと思います。

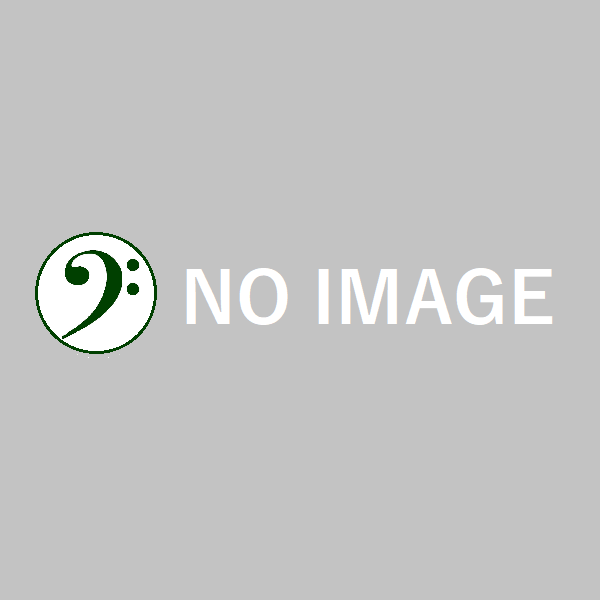


コメント