一時期かなり流行っていたアナログディレイです。
独立したモジュレーションのコントロールが特徴です。
さらに、バッファーのON/OFF機能も備えています。
かつての超人気機種
最近はあまり流通していないようですが、数年前には「エフェクター愛好家の足元のアナログディレイといったらほぼこれ」というぐらい多くの人が使っていた記憶があります。
ベースの動画はいいのがなかったのでギターでの演奏になりますが、こちらが分かりやすいです。
0:45あたりから発振音が聴けます。
このディレイ、「マーク2」というぐらいなんで旧型も存在するんですが、見た目はまったく同じで、判別方法は基板の色(初期モデルは緑、新型は青)しかないようです。
基本的な機能は同じですが、新型はモジュレーションの調整範囲やバッファーの設計が見直されているとのことでした。
コントロールの特徴
コントロールは、通常サイズのノブがTIME(ディレイタイム)、MIX(エフェクト音の音量)、REGEN(フィードバック・ディレイ音の回数)の3つ。
上部にはミニサイズのコントロールが並んでおり、MOD(モジュレーション)のON/OFFスイッチ、SPEEDとDEPTHのノブ、そしてT/B(トゥルーバイパスとバッファードバイパスの切替)スイッチとなっています。
冒頭にも書いたとおり、このディレイはディレイ音に効くピッチモジュレーションを備えているのがポイントです。
コーラス的な雰囲気にはなりませんが、DEPTHのセッティングにより、テープエコー的な揺れから、ディレイ音の音程がぐわんぐわん上下する飛び道具的な揺れまで幅広く調整できます。
また、SPEEDで調整する揺れの速さと連動して左上のLEDが点滅するので、モジュレーションのスピードを視覚的にも確認できます。
そして、T/Bのスイッチを押して右上のLEDが点灯した状態だとバッファードバイパスになり、エフェクトOFF時にもバッファーが効くようになります。
バッファーONだとディレイ音の音質がクリアになり、トゥルーバイパス時と比較してくっきりした効きになるので、個人的にはバッファーONの音が好みでした。
なお、バッファードバイパス状態でもOFFにした後ディレイ音が残ることはなく、残響はバサッと切れます。
発振好きにもオススメ
で、このディレイは何がよかったかというと、太く攻撃的ながら鋭すぎない発振音がとても気に入っていたのですが、それに加え発振操作のしやすさが非常に素晴らしかったです。
過去に所有していたモジュレーション機能付ディレイだと、SubdecayのAnamnesis Echoというのがありました。

こちらも気に入っていましたが、MXRサイズの筐体に5個のノブがひしめき合っていたため、ディレイタイムだけグイッと操作するのが難しい、という欠点がありました。
しかし、EKKO 616はモジュレーション機能のノブをミニサイズにすることにより、パッと触れるつまみはディレイの基本機能をつかさどる3つだけになっているので、的確に発振音を操ることができるのです。
ミニサイズエフェクターによく採用される小さなノブには賛否ありますが、このエフェクターに関しては大正解だと感じました。
Lofi EKKO 616 MKⅡやEKKO 616 MKII DARKといったバリエーションモデルも存在しますが、いずれも最近は国内ではあまり見かけません。
他のエフェクターではあまり見られない工夫が詰まったディレイですので、気になる方は見かけたら即座にゲットすることをおすすめしたいです。
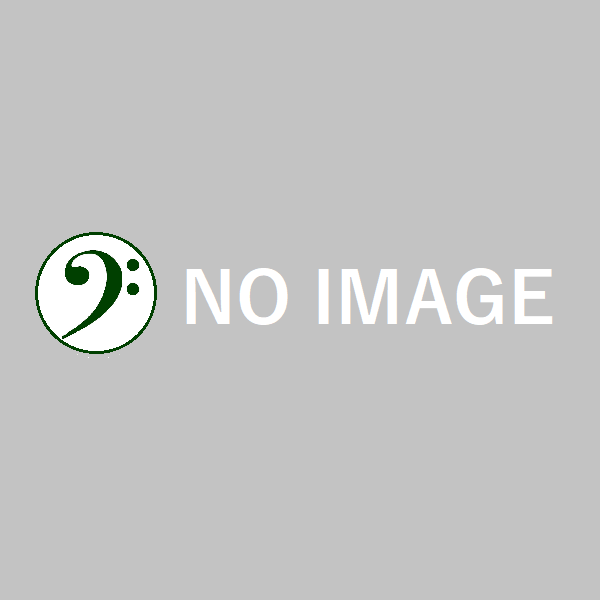

コメント