11種類(実質それ以上)のリバーブモードを備えた、エレハモの多機能エフェクターです。
近年のエレハモのデジタルエフェクターだけあって、見た目以上の機能が詰め込まれています。
電源はDC9Vアダプター(※専用アダプター付属)、電池駆動はできません。
音色とコントロールの特徴
ベースでの動画はなかったので、ギターですがこちらのオフィシャル動画をご覧いただければと思います。
毎度のことながらエレハモの公式動画は製品の魅力を余すことなく伝えていますが、輸入代理店が字幕つきのものをアップしていました。
パッと見た感じのコントロールはシンプルです。
FX LVLはリバーブ音の音量で、最小のときは基本的に原音だけが鳴ります。
このFX LVLは、2時方向あたりより上げると原音が小さくなっていくので、全開にすれば残響音だけが鳴るキルドライにもできます。
TIMEはリバーブの残響の長さです。
TONEはリバーブ音に効くトーンで、残響音が反時計回りで暗く、時計回りで明るくなります。
モードによっては人工的な音になってしまうので、場合によって絞り気味にする方が良いケースもありました。
これら3つのノブに加え、11種類のリバーブを切り替えるセレクター、そして中央にMODEという小さなボタンがあります。
一部のリバーブにおいてはMODEボタンを押すことでさらに音色を細かく切り替えることができますし、MODEボタンの長押しにより、表に出ていない隠れたパラメーターを調整する「セカンダリーノブモード」に入ることができます。
内蔵リバーブの種類
リバーブの種類は、定番のものとしてはHALL、SPRING、PLATEの3つ。
そしてそのほか、様々な変わり種リバーブを備えています。
(以下、動画内での登場時間を記載。動画の順番どおりに紹介するので、セレクターの操作とは順番が異なります)
SHIMがここ数年でメジャーになったシマーリバーブ(2:04~)。
残響音にオクターブ上のキラキラした音が加わり、オルガンのような幻想的な音になります。
このOCEANS 11に限らず、シマーはベースに使うと濁った感じの音になってしまうので、ギターのような綺麗な雰囲気にはならないのが残念なところですが、6弦ベース等の高音域なら効果的に使えます。
REVRSはリバースリバーブ(2:46~)です。
ディレイだとリバースモードがあるものも珍しくないですが、リバーブだとあまり見ないですね。
弾いた音に対し、だんだん音が大きくなる逆回転の残響が「ぅふわあっ↑」とついてくる、独特の音です。
TREMはトレモロ(音量が上下するモジュレーション)とリバーブの組み合わせ(3:33~)で、動画内で「ベースと相性がいい」とコメントされています。
これはバリトンギターですかね?低音部での音色も聴けます(4:12~)。
DYNA、ダイナミックリバーブ(7:05)は、楽器の原音を邪魔しないように残響音が徐々に大きくなったり、ゲートがかかって残響がバッサリ切れたりするリバーブをMODEボタンで切り替えられます。
キルドライ状態だとかなり面白い効果が得られ、ボリューム奏法みたいなことも可能です。
POLYは、リバーブ音にオクターブ上下の音を付加する、和音に対応したポリフォニックオクターブリバーブ(8:08~)です。
残響にエレハモのPOGをかけたような、パイプオルガン風の音になります。

AUTO-INFはオートインフィニティリバーブ(8:59~)で、弾いた音を次の音が鳴るまでの間、自動でずっと伸ばし続けてくれるという、エレハモのSUPEREGOに似たことができる機能です。

MODはモジュレーションリバーブ(10:00)。リバーブ音にモジュレーションが加わります。
MODEボタンの切り替えにより、コーラス、フランジャー、コーラス+フランジャーの3種類から選択可能です。
フランジャー+リバーブといえばエレハモのリバーブ、Holy GrailでおなじみのFlerbですね。
そして、ECHOがリバーブとディレイの組み合わせ(11:13~)です。
素の音も必要十分なクオリティ
以上、盛りだくさんの機能を詰め込んだ、いくらでも遊べるリバーブです。
残響の自然さでは高級機にはかないませんが、TONEがついているのは大きいですし、ドライ音が引っ込んだりするようなこともなく、普通のリバーブとしても十分実用的に使えます。
エフェクトをOFFにした際、残響を残すかバッサリ切るかも内部のスイッチで選択できるうえ、フットスイッチ長踏みで残響音を伸ばし続けることさえも可能です。
見えないパラメーターがあるのには個人的になかなか慣れなかったのですが、この多機能をMXRサイズで実現しているのが凄いです。
予算を抑えつつ面白さ重視のリバーブを探すなら、現状これ以上の選択肢はないと言っていいでしょう。
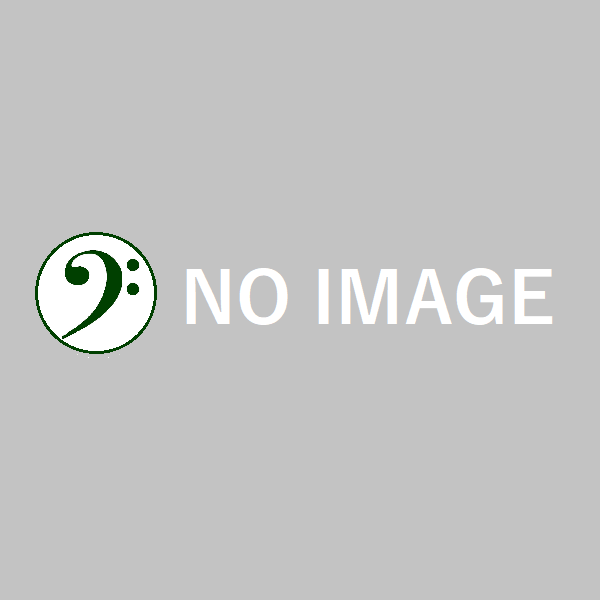

コメント